May 30, 2024
_連携大学院を担わせて頂いている東北大学 大学院医学系研究科の募集要項が発表されました。令和6年10月または令和7年4月入学が可能となります。成育にある私たちの研究室で研究を行って頂くことで、大学院の学位が取得できます。
_出願にあたっては全面的にアシストしますので、前もってお知らせ下さい。
森雅樹(mori-ma@ncchd.go.jp)
_本日発表された願書はこちらとなります。
出願受け付け期間は7月1日から12日までとなっております。ご検討の方は出願前にお伝えください。
May 21, 2024
私たちの研究室では現在、研究員・研究補助員の募集を行っています!
詳細は森まで御連絡下さい (mori-ma@ncchd.go.jp)。ご見学に来ていただくことも可能です。研究のゴール設定や勤務シフトはご相談に乗ります。
下記が成育医療センターの募集ページとなります。
お気軽に御連絡下さい。また、大学院生の募集も行っています。東北大学や東京医科歯科大学の連携大学院を通して成育で学位取得して頂くことが可能です。大学院への願書締め切りは7月上旬となっております。こちらも詳しくは森までお知らせ下さい。
May 10, 2024
参加させて頂いている学術変革領域A 「多細胞生命自律性」のウェブサイトで私たちの研究チームの紹介ページを作って頂きました。
May 9, 2024
成育医療センターの再生医療センターで研究セミナーをさせて頂きました。
再生医療センターではES細胞から分化させた肝細胞を臨床応用して活用するなど幹細胞治療の先端を担われています。
_私の発表にも多くの質問を頂き、とても有意義な機会となりました。
April 20, 2024
老化の研究会で発表 (@熊本城ホール) を行いました。熊本は初めてでしたが良いところでした。
老化研究のフィールドはとてもユニークで、大きくスコープの異なる研究者が一堂に会します。人柄の素敵なまた会いたくなるような人にたくさん出会えます。免疫、再生、血管、代謝、がん、皮膚、筋、神経などのさまざまな観点から細胞レベルの老化、および個体レベルの老化に挑んでいます。私たちの研究グループは「若年性」という小児に特有の性質を調節するしくみが老化や早老症と関連する仮説の検証に取り組んでいます。私たちの着眼は細胞レベルの小児ならではの性質を実現する代謝メカニズムや分子複合体の合成などにあります。それぞれの方向軸をもった研究者と相互作用できることがこのような領域に参画できる利点です。
散会後、会場からすぐの熊本城を訪れ、城郭のとても端麗な姿を見ることができました。震災後の修復がなお続いており、まだ癒えてはいないことがわかりました。また訪れることができるときを心待ちにしたいと思います。


April 1, 2024
研究室を国立成育医療研究センターに移動しました。
_新しく作られた小児生理学研究部の研究室を子どもたちや家族のためになれる研究を実践する場として盛り立てていきます。
_新しく研究員さんを募集中ですので、大学院生・博士研究員・補助研究員・秘書としてチームに加わって頂くことにご興味をいただける方はご連絡ください。時期や勤務時間は柔軟に対応できます。よろしくお願いいたします!
_連絡先はmori-ma[at]ncchd.go.jp ([at]を@に代えて下さい) です。
December 6, 2023
第46回日本分子生物学会 (神戸) に参加しました。中西 未央 先生 (千葉大学) と松田 充弘 先生 (ドレスデン工科大学) がオーガナイズされたシンポジウム「発生・再生の時を刻む時計の理解と制御」で研究発表をさせて頂きました。
_研究の世界では、共通の謎に挑む研究者が世界の各地から一同に会し、初めて会ったのに旧知の仲のように口角泡を飛ばしながら議論することができます。懇親会の場では初めて話す研究者ばかりでしたが旧友を得たような気になりました。会が終わればそれぞれが自分の地に戻り、研究を発展させます。またこのような素敵な場に混ぜてもらえるように頑張らねばなりません。
シンポジウム 『発生・再生の時を刻む時計の理解と制御』
若年性研究が明らかにする新たな分子機構と難病の治療戦略
森 雅樹
October 11, 2023
第68回 日本人類遺伝学会 (東京) で研究発表を行いました。
_海外から多くの遺伝疾患にかかわる研究者や臨床家が参加して国境をひとまたぎに闊達な議論が行われました。意見交換を促進するためスマホを使ったリアルタイムの意見投票をしたり、新しい工夫が取り入れられていました。
_技術革新に伴い遺伝子検査はコストが下がり精度が上がっています。臨床現場においてもその重要性が増し、位置づけに変化が起きています。
学会に参加するとどうしても狭くなりがちな視野を広げてもらえます。新しいパラダイムや概念がどんどん生まれています。それをオープンに受け入れられる柔軟さと好奇心が大切だと思い知らされました。
森はメタボローム研究について報告しました。貴重な意見の交換ができました。
ポスター発表
Age-dependent metabolic shifts differentiate sarcopenic responses in mice
森 雅樹
July 8, 2023
小児循環器学会で研究発表を行いました。
研究室では日頃どうしても基礎的な生物学の興味が強くなりますが、小児循環器学会では多くの臨床的な発表や技術進歩に触れることができ、いつもと違うアイデアがたくさん湧いてきました。尊敬している研究者にもお会いして話すことができ、モチベーションを上げて帰ってきました。フィールドの一足飛びの進歩についていけるように、しっかりと自分の研究を進めていかねば!と思いました。
森は下記のテーマでシンポジウムでの発表とポスター発表を行いました。
シンポジウム『オミックス解析がもたらす小児心血管疾患研究の新たな展開』
新たな再生治療戦略の確立を目的とした若年期トランスクリプトームの実像解明
森 雅樹
ポスター発表
若年性研究による小児特有の生理機構の解明
森 雅樹
May 28, 2023
老化の研究会に参加しました。事業を担われているAMEDの担当者様が結局のところ研究者がどのようにしたら良い研究ができるかを考えて身を粉にして下さっていることが目に見えました。研究者は個性的ですし、仕事量的にも並のタフさでは勤まらない役回りと思いましたが、事業に息を吹き込むために大いに知恵と感情を使って下さっていることがわかりました。こちらとしては少なくとも研究のパートをしっかり担わねば!と思ったのと同時に、何から何まで自分でやろうとせずに任せたり頼ったりできる人達に支えられているし、期待もされているのだと思いました。
なんと20年ぶりとなる研究室の先輩とも再会できました!! 私は当時20代でした・・。当時私は今にも増して若輩者かつ生意気で未来に望みをかけるしかない学部学生でしたが、その先輩が大学院生としてラボに加入され、初回の研究セミナーの一言目で、担当されることになった研究テーマが抱えている課題や本質的なクエスチョンを簡潔に述べられたことに衝撃を受けたのが忘れられません。研究者の貴重なお手本を見させて頂いていることに私はまだ気づいていませんでした。これからがとても楽しみになり、非常にやる気が出ました!
March 15, 2023
心血管内分泌代謝学会学術 (CVEM) オンライン講演会で研究発表を行いました。山城 義人 先生、有馬 勇一郎 先生が先頭に立って開催されているCVEMの講演会で口頭発表をさせて頂きました。若い研究者や重要なコンセプトを確立した研究者が集って発表を行い、クオリティの高い研究結果に基づいて意見を交換し、予期せぬ展開を生みそうな貴重な場となっています。
March 14-15 , 2023
第10回 細胞競合コロキウムに参加しました。細胞競合コロキウムは京都大学の藤田 恭之 先生 (ヤスさん)と井垣 達吏 先生が発起人となり10年前から毎年開かれている若手が大活躍する研究会です。研究テーマは細胞競合に限定されておらず、私たちのグループからも大学院生の塚村篤史さんと研究員の東香織さんがそれぞれ口頭発表を行いました。東さんは10人以上から質問してもらい、塚村先生も時間の制約で3人の方から質問をしてもらいました。私たちにとって刺激となる空気感でしたし、虚心坦懐にサイエンスと向き合う体勢を整える機会となりました。発表者は大学院生や学部生が多く、5分 (~10分) など短い発表時間でも驚くほど上手くバックグラウンドを説明していて、深い研究内容にきちんと入ることができていました。決して簡単ではない研究背景や結果を説明するためのイラスト図も丁寧に作られていました。多彩な角度からなされる質問に論拠を粘り強く述べ自分の主張をディフェンスしていました。英語での質疑も闊達でした。端的に返答することが困難なときも、愛嬌のある人間的なやり取りで次につなげていました。研究にエネルギーが吹き込まれて、数多くの研究が進んでいきます。
December 15-17, 2022
人類遺伝学会に参加しました。森は2演題の口頭発表を行いました。人類遺伝学会は主にヒトの遺伝子やゲノム研究のエキスパートが集います。私は「子どもの成長・発達」がそのような仕組みで実現しているか知りたくて、遺伝子を第一の研究対象にしているのでとても勉強になります。遺伝子の多様性に原因がある病気の研究や、遺伝子の基本的な働きかた、病気の研究の方法などについて幅広く研究発表と議論が行われました。
分身ロボットカフェと呼ばれるカフェスペースがあり、病気のため外出困難な方々がパイロットとして遠隔で操作して接客して下さいました。コロナで初対面の人と話す機会がとても減ったので、久しぶりにかしこまらずに仕事以外の会話をすることができました。
学会では自分の研究戦略についての貴重な意見を頂きましたし、ユニークな技術についての発表も多く聞けました。学会に参加すると自分の立ち位置や見つめるべき方向性が浮き彫りになることが多いのですが、今回もそのような経験ができました。
December 13-15, 2022
変革領域「多細胞自律性 (マルチセルラーオートノミー)」の研究会に参加しました。細胞競合の第一線の研究を担う研究者を含め、領域に参加する研究者の口頭発表が行われ、ポスター発表も開かれました。森は現在とこれからの研究内容について発表しました。
トークの終わった瞬間に質問者がマイクに列をなし、それぞれのトークに10分の質疑時間が設けられていたのですが、質問が終わりきらないこともしばしばで、極めて闊達な意見交換がなされました。私からすると個々の研究者は極めて優れていて教えてもらう一方なのですが、そのような方々が質問やディスカッションを非常に重視しておられることに、研究にとっての交流の重要性を感じました。
また、よりオープンな意見交換の場も設けられ、いろいろなキャリアを積んでいる研究者と研究のオーガナイズのしかたや研究フィールドの動向などについて教えてもらったり意見を交わしたりしました。コロナ対応もしっかりなされていました。研究者の顔を見て、生の声で意見交換できて、発表者も参加者もどこかひとしおの喜びを感じながら議論を交わしているように思われました。

November 20, 2022 Science illustrators
cattell様 (https://www.cattell-labo.com/) に依頼して細胞のイメージ像を描いてもらいました。
サイエンスの知見をわかりやすく伝える技術を提供して下さるイラストレーター様達に感謝です !!
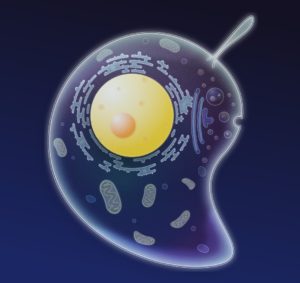
September 30, 2022
_私たちの研究室からの研究提案「生体機能の最適化機構としての老化の再定義」がAMED-PRIME「根本的な老化メカニズムの理解と破綻に伴う疾患機序解明」に採択されました (関連ページ)。生命の根本的なクエスチョンである老化の仕組みに、若年性生物学や先端の科学技術を駆使して挑みます。
August 1, 2022
_私たちの研究室が取り組んでいる「細胞競合」の研究提案が、「学術変革領域(A) 多細胞生命自律性 Multicelluar Autonomy」に採択されました。細胞競合は、生命が多くの細胞から構成されることでどのような内部的な関係性が発生するのかを解き明かす根本的な視点です。細胞が多様性をもつことで変化への適応性を上げることもできますし、大きく逸脱した細胞がガンなど病気を起こすことも考えられます。一方、生命として成立するためには多様性を収斂させて統合性を保つことも必要です。細胞の社会性を取り扱う生物学的な枠組みに、先天的な病気の視点から取り組みます。
July 21-23, 2022
第58回 日本小児循環器学会・学術集会で研究発表を行いました。
大学院生の塚村さん (口頭発表)、森 (ポスター発表とシンポジウム講演) が研究について発表する機会を与えて頂きました。
塚村 篤史、森 雅樹
「若年性生物学の取り組みによる小児循環器難病に対する新規治療戦略の確立を目指して」
口頭発表
森 雅樹
「若年性に着眼した循環器難病の新たな再生医療戦略への取り組み」
シンポジウム テイラーメイド医療から創薬まで ~生物工学の発展と小児循環器領域への応用~
森 雅樹
「若年性生物学を通した小児循環器難病の治療戦略探索」
ポスター発表
June 30 - July 3, 2022
第45回 日本神経科学大会で研究発表 (口頭) を行いました。
Masaki Mori
"BEX1, a juvenility-associated gene, is essential for ciliogenesis."
第45回日本神経科学大会、口頭発表
Apr 11, 2022
東さんがLab manager兼Researcherとしてラボに加入して下さいました。
Mar 12, 2022
川野小児医学奨学財団の成果報告会が開かれ、1年間の研究助成を受けた研究者として報告の研究発表をさせて頂きました。(比較的) 若い研究者にとって、財団による研究支援は極めて不可欠な助けとなります。研究者を支え、また手間暇を惜しまず、財団を運営し、研究助成の事業を行い、今回のような発表会の場まで整えて下さる関係の方々に頭が下がります。大げさでなく、このような財団の方々の支援がなければ、若手研究者は研究ができなくなります。オンラインの開催でRemoを用いて行われましたが、Remoでは参加者と個別の話もしやすく、そのような気配りもされていました。
発表内容としては、臨床・基礎研究・社会医学の幅広い方面から進んでおり、またそれらの間の融合も起きつつあることがわかりました。例えば、臨床の第一人者が基礎研究から生まれた成果を患者さんにとどけていました。また、社会医学の研究では、基礎研究の視点からも問題の解決となる重要な前進について伺いました。
基礎研究でも、分子生物学の手法を駆使して治験に進むプロセスであったり、臨床と基礎の両方を駆使して進めるアプローチについて伺うことができました。たゆまぬ取り組みと高い技術力と信念に基づいて、目の前の課題に取り組み続ける姿勢でした。
Mar 11, 2022
遺伝子難病のモデル生物解析を行っている研究者の集まる研究会で研究発表を行いました。病気は、非常に複雑で深淵なシステムである生命が一部に破綻することで起きます。病気の起きる機序を調べ、治療の手段を開発する過程では、モデル生物を対象とした研究が不可欠になります。現在特によく対象となる生物は、ゼブラフィッシュやメダカ、アフリカツメガエル、マウスやラット、線虫、キイロショウジョウバエなどを含みます。モデル生物を活用した研究を行うことで、患者様で同定された遺伝子の変化がどのようにして病気につながるのか、またどうすれば治せる可能性があるのかを具体的に検証することができます。私も自分の研究発表を行い、他の研究者の先生方の話を聞くことで、解決すべき課題が浮き彫りになりました。患者様に利益を還元できるように研究を進め行きます。
Feb 11, 2022
We published a paper that describes the role of Bex1, a juvenile-expressed IDP (intrinsically disordered protein) in ciliogenesis and tubulin polymerization. We would like to thank the scientists that contributed to the research!
BMC Biology, 2022
https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-022-01246-x

Sep 11-12, 2021
国立循環器病研究センターで行われた第5回BCVR (Basic Cardio Vascular Research, 循環器基礎研究フォーラム) で研究発表を行いました !
Masaki Mori
"Age-dependent alternative splicing (ADAS) establishes juvenile transcriptome of cardiovascular systems"
BCVR 第5回日本循環器学会基礎研究フォーラム、口頭発表
Atsushi Tsukamura, Masaki Mori
"Cytoophidia-forming capacity of juvenility-associated proteins"
BCVR 第5回日本循環器学会基礎研究フォーラム、口頭発表
Jul 9-11, 2021
第57回日本小児循環器学会学術集会で研究発表を行いました !
森 雅樹
「若年性に着眼した循環器難病の新たな治療開発への取り組み」
第57回日本小児循環器学会学術集会、口頭発表
Apr 22, 2021
We published a paper that describes a role of TBC1D24 that forms "Cyto-ophidia", meaning a snake in a cell, thereby modulating the GTPase enzymatic activity. Dr. Morimune, the 1st author made a tremendous effort to reveal the new function of the epilepsy-associated protein.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248517

Oct 22, 2020
We published a paper that describes the loss of cellular juvenescence specifically occurring in the “loser cells” in cell competition.
https://www.nature.com/articles/s41598-020-74874-4
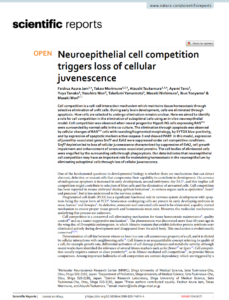
2020年2月18日 私たちの研究室からの論文が出版となりました。
私たちの研究室からの論文が出版されました。日々、多岐に渡り研究を支えて下さっている皆様に心より感謝申し上げます。
Title: Srsf7 establishes the juvenile transcriptome through age-dependent alternative splicing in mice.
Authors: Yosuke Kadota,*, Faidruz Azura Jam,*, Haruka Yukiue,*, Ichiro Terakado, Takao Morimune, Ayami Tano, Yuya Tanaka, Sayumi Akahane, Mayu Fukumura, Masaki Mori
[*These authors contributed equally to this paper.]
iScience, 2020.

2019年12月25日 森宗さんと門田さんが審査員特別賞を受賞されました。
12月10日に行われた第36回滋賀医科大学シンポジウムで行った研究発表につきまして、大学院博士課程の森宗さんと門田さんが「審査員特別賞」を受賞されました。森宗さんの研究演題名は「若年性lncRNAとてんかん性脳症関連遺伝子との相互作用」、門田さんの研究演題名は「lncRNAのヒト-マウス間での進化的保存性について」でした。森宗さん、門田さん、おめでとうございます。
滋賀医科大学シンポジウムを多忙を縫って準備して下さり、貴重な研究発表やディスカッションの場を作って下さった准講会の教員の先生方と研究推進課の皆様に心から感謝いたします。
2019年11月16-17日 第46回日本脳科学会を主宰しました。
滋賀医科大学 神経難病研究センター主催で、第46回日本脳科学会が開催されました。私も事務局長として学会開催の実務につきまして経験させていただきました。各所におきまして、それぞれの方が工夫を凝らしたり、精力的に準備に取り組んで下さり、そのおかげで学会が非常にうまく進んだと思います。
研究発表についても、技術や精度の高いものが多く、脳科学の広い分野の方々が集まって議論できたことは、今後も大きな発展につながると思いました。若手研究者対象の奨励賞につきましては、私達の研究グループから、大学院博士課程の門田陽介さんと学部生の雪上晴加さんが受賞されました。門田さん、雪上さん、おめでとうございます。日々、実験や解析に取り組んだ成果だと思います。ただし今回の学会でもわかったように、脳科学はフィールドが広く、考えることのできる切り口は多いですし、知識として身に着けたり、経験したりせねばならないことは無数にあります。講演では多くのロールモデルの研究者の話を聞けました。私達も、それをお手本にして、前に進んで行きたいと思います。
2019年10月26日 若鮎祭
滋賀医科大学の学園祭 「若鮎祭」 の会場で、研究などへの姿勢が認められ、研究医の田埜郁実さんに学長賞が授与されました。田埜さん、おめでとうございます。
2019年10月3日 研究医セミナーが開かれました。
令和元年度 第1回 滋賀医科大学研究医セミナーが開かれ、私たちの研究室からは学部3回生の雪上さんが口頭発表を行いました。研究医セミナーは、これからの研究を引っ張る若い研究者を育てる取り組みです。発表した学生さん達は、それぞれが見据える方向性を模索しつつ、研究室で行われている研究に携わっていました。ランチも提供され、肩ひじはらずに研究を楽しめる機会です。
2019年8月16日 高校生が研究室に滞在しました。
研究や医学に興味のある1人の高校生に2週間、研究室に滞在していただきました。高度な実験技能を習得するには十分な時間ではないのですが、若い時期の感受性は研ぎ澄まされていますし、いろいろなことを感じ取ってくれたのではないかと思います。慣れない土地で知らない環境に飛び込んで、年代も違う人と会うことは、非常に勇気のいることです。心理的なハードルを越えられることが尊敬に値します。高校生の成長スピードに負けないように、私たちも研究を進めて行かねばなりません。
2019年7月31日 IRUD Beyondの研究報告会 (東京) で研究発表を行いました。
未診断疾患イニシアチブ (IRUD) の枠組みの中で進められている研究プロジェクトに、IRUD Beyond: 【Beyond genotyping】 「モデル動物等研究コーディネーティングネットワークによる希少・未診断疾患の病因遺伝子変異候補の機能解析研究」 があります。私たちの研究グループは、この一部として、遺伝子疾患の研究をさせていただいています。中間報告として、研究の進捗を発表しました。
小児難病の治療法開発を見据えた研究に取り組んで参ります。
2019年7月31日 令和元年度学長裁量経費(若手萌芽研究)による研究助成
令和元年度学長裁量経費(若手萌芽研究)による研究助成(公募)の審査結果が開示され、私たちの研究室から、大学院生のFaidruz Azura Jamさん、門田 陽介さんの研究計画が採択となりました。このような若手研究者を支援する枠組みを作り、運営して下さっている方々に感謝申し上げます。
2019年7月25~28日 第42回日本神経科学大会 (新潟) で研究発表を行いました。
ニューロサイエンスの幅広いフィールドの研究を目の当たりにしながら、自分たちの研究のベクトルを位置付けました。
小児難病の治療法に繋がりそうな発見や研究成果をいくつも伺えました。小児難病の治療の道筋は多く、それを実現に結び付けることは、研究者の役割が大きいです。
ポスター会場でも、非常におもしろい研究をシェアしていただき、貴重な実験技術のお話もお伺いでき、発奮して帰って来ました。
2019年7月18日 新学術領域「脳構築における発生時計と場の連携」 第4回領域会議で研究発表を行いました。
新学術領域「脳構築における発生時計と場の連携」 第4回領域会議 (7月16~18日、金沢) に出席しました。
私達の研究室からは、大学院生のAzuraさんと門田さんがポスター発表を行い、私は口頭発表を行いました。Azuraさんは、「優秀ポスター賞」を受賞されました。Azuraさんのこれまでの頑張りの成果です。2時間に及ぶポスター発表タイムの後、「友達を作れた」とAzuraさんが報告してくれましたが、それが何より価値のあることです。それぞれの学生さんが、自らのアイデアをディスカッションの遡上に載せて、忌憚のない意見を得られたと思います。これからの研究の前進につながります。
私も、未踏の仮説に挑む研究をたくさん伺えて、貴重な出会いの場を与えて頂き、かなりの刺激を受けました。一歩一歩前に進んで行きたいと思います。
2019年5月31日 第61回日本小児神経学会学術集会 (名古屋) で研究発表を行いました。
5月31日から6月2日に開催された第61回日本小児神経学会学術集会で研究発表を行いました。大学院生の森宗さんと森がそれぞれ発表を行いました。
森宗さんは、優秀ポスター賞を受賞されました ! おめでとうございます。(演題名: 「若年特性を活用した小児神経疾患の治療戦略」) ポスターの発表時間を通して、途切れることなく訪れて下さった多くの方々にわかりやすく研究内容を説明しました。研究はさらに興味深い展開をむかえており、今回いただいたフィードバックをもとにさらに発展できそうです。
英語で発表が行われるEnglish Sessionがたくさんあり、海外の研究室や企業からも含め、多彩な参加者が集っていました。多様なアイデアやアプローチから、小児神経疾患の治療に向けた研究が進んでいく様を見ることができました。
2019年4月21日 第122回日本小児科学会 (金沢) で研究発表を行いました。
第122回日本小児科学会で研究発表を行いました。大学院生の森宗さんと私がそれぞれ研究発表を行いました。森宗さんの発表に対しては、小児難病の診療および研究に深く携わっておられる先生から、「希望を抱けた」とコメントいただき、エールを送っていただいた気持ちになりました。私たちが取り組んでいる若年特性 (小児特性) は、動物モデルの解析を行っており、病気との関連を検証していきます。
現在、診断のついていない患者様の遺伝子を解析して、診断・治療法の開発につなげる全国的な事業 (IRUD, アイラッド) が続いています。ゲノムシーケンシングによる未診断疾患の遺伝子解析がなされ、これまでは診断の付かなかった症例の約30パーセントで診断がつくようになっています。上手く診断がつき治療に結び付けられた場合のクリニカルコースの改善は著明であり、その手順を生み出すのは研究者の重要な役目です。私たち研究者の役割は、患者様から見つかってきた遺伝子の異常がどのようないきさつで病気につながるかを明らかにし、治療に結び付けることです。現在、そのような研究も行なっており、はたらきが全く知られていないけれども、病気の原因になっている遺伝子の機能解析を行っています。
バイオバンクについての多くの研究発表がありました。バイオバンクは、コホート解析で集められた検体や患者様の情報を広く活用できるように整備する事業です。現在、そのバトンは、利活用すべき研究者の側にあることがわかりました。
旧知の先生方にもお会いすることができました。今回お会いすることのできた小児科医や研究者、製薬企業の方々と、今後また上手く進んで行けるように、ひとつひとつ取り組んで参ります。
2019年3月25日 SUMSグランドラウンド研究発表への授賞式がありました。
今年度4月24日に行われたSUMSグランドラウンドでの研究発表に対して、学部生の雪上晴加さんが優秀賞を受賞されました。日々の努力が報われたと思います。学部生さんは、知識や経験は多くないかも知れませんが、だからこそ可能な自由な発想や疑問があり、チャレンジングな目標を設定することができます。そのような良さをさらに伸ばしながら、技術や知識・方法論の習得につなげていってくれたらと思います。
2019年3月9日 卓越研究員制度の公募説明会で、若手研究者講演を担当しました。
卓越研究員制度の公募説明会 (文部科学省、日本学術振興会) が開かれ、若手研究者講演を担当しました。若手研究者を取り巻く環境には、数々の課題があります。それらは、雇用の不安定性や、研究遂行における独立性および予算執行における独立性を含みます。そのことについての問題提起や若手研究者の立場でなせることについて考えを述べました。
私はすでに“若手”研究者ではありませんが、現在所属している滋賀医科大学では、上記の課題はうまく解決されていて、研究に向かい合うことができています。
上記のような課題が存在しながらも、研究をつづけている若手研究者には選りすぐりの人材が多く、その方々が安定的に継続して主体的に研究することができたらと思います。
2019年3月8日 研究授賞式が開かれました。
昨年12月10日に行われた滋賀医科大学シンポジウムの研究発表について審査結果が発表されました。大学院生の門田陽介さんが若鮎賞を、学部生の田埜郁実さんが奨励賞を受けました。学生さんそれぞれの日々の努力が報われました。このような若い研究者の育成機会を毎年準備・開催されている准講会の先生方に感謝申し上げます。学生さんたちにとっては、発表に向けての準備や、発表での緊張やリアルタイムの議論に刺激され、受賞の如何に関わらず、学びの機会になったと思います。賞をいただいた学生さんはいっそう謙虚になり、周囲の方々からの眼に恥じないよう研鑽を積み重ねていって欲しいです。
2019年3月5日 私たちの研究室からの論文が受理となりました。
私たちの研究室からの論文が受理となりました。御指導をいただいた先生方や、研究を日々に渡り支えて下さった皆様に心より感謝申し上げます。
Title: Juvenility-associated lncRNA Gm14230 maintains cellular juvenescence
Authors: Ayami Tano1,#, Yosuke Kadota1,#, Takao Morimune1,2,#, Faidruz Azura Jam1, Haruka Yukiue1, Jean-Pierre Bellier1, Tatsuyuki Sokoda2, Yoshihiro Maruo2, *Masaki Mori1
(#, equally contributing authors)
Journal of Cell Science, 2019.
2019年3月4日 第2回IRUD-Beyond モデル生物 国際シンポジウム (東京) に参加しました。
第2回IRUD-Beyond モデル生物 国際シンポジウム (東京) に参加させていただきました。
小児科医としての経験から、IRUD (アイラッド) のように難病の患者様の原因遺伝子を同定して治療につなげる事業に貢献したい気持ちをずっと持っていました。現在は、IRUDの事業が、遺伝学アプローチを効率良く用いられるモデル生物研究とうまくかみ合っていることがわかりました。このモデル生物研究により、変異遺伝子のアノテーションがついていくのだと思います。私は現在、げっ歯類 (ネズミ) をモデル生物として研究をしていますが、なぜそのモデル生物で研究するのか、その意義を常に認識していねばならないと思いました。
印象的だったのは、「n=1問題」に論が及んだ時でした。n=1問題とは、患者様が1人しかいらっしゃらないとき、遺伝子の変異が病気の原因になっていると限らないという問題です。現在広く行われている遺伝子解読 (エキソーム解析) は、タンパク質に対応する約1%のみを解読するので、残りの99%に原因がある可能性が否定できません。しかし、もし2人以上の患者さんが同じ遺伝子の異常をもっていたら、その遺伝子が病気に関わっている可能性が高まります。本来なら、日本国内に2人目の患者様が見つかることを待つしかなかったかも知れませんが、国境を越えて、他国の研究者と協力できたら、あっという間に多くの患者が見つかる可能性が高まります。実際そのような事例が多いようです。カナダから参加された研究者たちが、信頼関係に基づく協力ができたら、患者様のためになれる契機が非常に大きくなることを指摘しました。
また、そもそも、IRUDが同定する遺伝子情報は、無償で研究者に提供されます。患者様の遺伝子情報は、研究者にとって非常に貴重です。
このように根底に流れる無償の協力姿勢は、極めて大きな力になり、研究を大きく促進すると思われます。
研究の世界には競争原理が働いており、国内でも例えば研究費を巡って苛烈な競争が課されますが、その原理が研究のすべてではないというごく自然なことを思い出しました。
2019年3月1日 第30回てんかん研究治療研究会 (大阪) に参加しました。
第30回てんかん研究治療研究会 (大阪) に参加させていただきました。非常に興味深い議論が活発に交わされ、たいへん刺激になりましたし、勉びの素材を与えていただきました。てんかん研究のフィールドがいかに脈々と広がっているかを垣間見ました。私たちが現在着眼している生命現象も、てんかんの病態理解や治療法の開発に何らかの貢献ができるよう研究を続けます。
2019年12月10日 シンポジウムで研究発表を行いました
滋賀医科大学 (SUMS) シンポジウムが開催され、私達の研究室から、大学院生の森宗 孝夫さん、Faidruz Azura Jamさん、門田 陽介さん、学部生の田埜 郁実さんが口頭発表を行いました。
4つの演題とも、複数の質問がオーディエンスからあり、学生さん自身の考えに基づいて応えました。いずれの学生さんも緊張したとのことでしたが、伝えるべきものは伝えられていたのではないかと思いました。
学生さんがそれぞれに行った練習の成果もはっきりと出ていました。
2019年11月10日 第45回 日本脳科学会で研究発表を行いました
第45回 日本脳科学会 (千葉大学主催) に参加しました。神経難病研究センター大学院生の森宗孝夫さんと森が口頭発表を行いました。
小児の脳発達を軸に、精神科・神経内科のアプローチで、臨床・基礎の研究者が一堂に介し、活発なディスカッションが交わされました。
次回、第46回 日本脳科学会は、滋賀医科大学で行われます! 今回は千葉大学の方々が非常にうまく学会を開催されているのを拝見し、学会準備の貴重なノウハウも伝授していただいて帰って来ました。今回のように良い学会になるように、準備を進めます。
2019年11月6日 SfN (Neuroscience2018) で研究発表を行いました
アメリカ神経科学学会 (SfN Neuroscience2018 San Diego) に参加しました。聞きしに勝る規模で参加者は総計2万8千人に及んだとのことでした。
おびただしい数の研究者が新しい考え・プロジェクトに挑戦しており、前向きなエネルギーを得ることができました。
私も演題を発表し、聞きに来てくださった方とのディスカッションから、今後につながるアイデアを得ました。
若い参加者が多く、数え切れないほどの新しいアイデアがそこかしこに生まれていました。
ポスター発表ではポスターの前に立っていなければならないと定められているのは1時間ですが、それ以外の時間も、自分のポスターの前や付近にいて、
自分の研究を積極的にアピールする姿勢の方が多くいました。
大学の同期の先生と会うことができて、また高名な研究者ともお会いする機会も作って貰い、実り多い学会参加になりました。
2019年8月22日 学長裁量経費(若手萌芽研究)による研究助成に門田陽介さんの研究計画が採択されました
滋賀医科大学の平成30年度学長裁量経費(若手萌芽研究)による研究助成(公募)の審査結果、私達の研究室の大学院学生 門田 陽介の研究計画「AI技術による若年性非コード長鎖RNAの種間保存性の全容解明と創薬標的としての開発」が採択となりました。門田さん、おめでとうございます!
2018年7月26~29日 第41回日本神経科学大会に参加、研究発表を行いました。
第41回日本神経科学大会に参加、研究発表を行いました。
口頭発表の多くやポスターの記載は英語で行われ、外国からの研究者の参加も非常に多くありました。必然的に研究スタイルも多様なものとなり、フィールドの広がりの広大さが感じられました。
有名なスピーカーもラフな格好で行い、若い学生との闊達な議論がありました。科学では自然な姿であり、研究の発展がさらに望めることに疑いありません。
学生さんの研究もたくさん聞きました。自らの考えで方向性や解析手段を考え、解釈や解決策に深く悩み、という姿でした。自信は持てていなかったとしても、オリジナリティのある本質的な研究をやっていて、研究者として育つ過程のさなかにあることがわかりました。なるたけ近視眼的になることなく進んで行ける研究環境を整備することがこちらの役割です。
声高に叫ばれている日本の研究力低下は、学生さん達のレベルでは杞憂であるという当たり前のことを改めて思いました。
2018年7月19日 基礎科学研究発表会
滋賀医科大学の基礎科学研究発表会で、当研究室の赤羽さん(研究医養成コース)が発表しました。自らのアイデアも含めて実験を立案・遂行し、わかりやすくプレゼンテーションしました。より本質的な疑問にも考えが至っていたと思います。実際に手を動かして実験をしたことで、さらなる疑問も浮かんで来たかも知れません。
他の研究室の学生さんも、研究に充てられたのは限られた時間でありながら、非常にユニークな内容でした。
2018年6月25日 長浜バイオ大学での講義を担当いたしました。
長浜バイオ大学での講義を担当いたしました。将来の臨床検査技師や他の職業を目指す学生さん達に、神経病理学のエッセンスを伝えることを目標としました。授業の中では、今後期待される新たな臨床検査技術について、たくさんの素晴らしいアイデアを学生さん達から聞くことができました。いずれも経験や体験に対する感性がなくては生まれ出てこないものだと思われました。大学も美しく研究機関としても設備が整っており、コラボレーションの重要性をひしひしと感じました。
2017年3月16-18日 第6回細胞競合コロキウムに参加しました
第6回細胞競合コロキウムに参加させていただきました (森、口頭発表、北海道)。昨年から2回目の参加でした。毎回、強烈なのが、若い研究者の議論の闊達さです。1つの発表毎に、つぶてのように質問がなされます。修士学生はもちろん学部生も発表しますが、研究に対するエネルギーに溢れ、研究内容もおもしろいし、質疑応答にあたっては、多数の縦横無尽な質問に自らの思考で主体的に答えます。(指導教官が代わりに答える‥‥ことはありません) ポスドクかと思って話していたら学生さんだったり、博士の学生さんだと思っていたら学部生さんだったり、研究に対する姿勢に加え、会話においても成熟した人柄であることが多く、わが身を振り返り初心を思い直す機会にいつもなります。
2017年3月2日 第48回大阪小児先進医療研究会 (大阪大学) でセミナーをさせていただきました
第48回大阪小児先進医療研究会 (大阪大学) でセミナーをさせていただきました。衝撃的であったのが、私がどうにか話した内容よりもずっと多くのことを、レスポンスとしていただいて帰ってきたことです。このような経験はかつてなく、研究会の充実ぶりをまともに受けました。
基礎研究を小児難病治療にいかに結び付けていくかには無数のアプローチがあります。コスト・時間はかかりますが、不可能ではないと考えています。その目標に向けて進むために、私よりずっと早くから同じ方向を真摯に見続けていらした方々の存在を改めて思い知り、心の底から激励される思いでした。
2017年1月17 -19日 細胞競合・ダイイングコード合同若手WS (大阪) に参加しました
細胞競合・ダイイングコード合同若手WS (大阪) に参加しました。当研究室からは、森、Azuraさん、Anarmaaさんが参加させていただきました。
若手が主役の会で、多くの情熱と鮮烈な才能にあふれた、かつ果断ない努力に裏打ちされたエネルギーあふれる研究発表をたくさん体感させていただきました。細胞競合のフィールドの研究会に何度か参加していますが、その都度、混沌としそうになる頭の中から、進むべき方向を指し示す光が前方に見える感覚を得て、帰ってくることができます。この方向になら、倒れても前のめりに倒れられそうです。
大学院生など若手研究者の、類稀な才能を目の当たりにすると、そのように自らの研究を展開させ、翼を広げることのできる環境をおそらく自ら作っているだろう若手研究者もすごいと思うし、そのような環境を構築されている研究室主宰者の努力や工夫にも思いを馳せます。
当研究室から参加したAzuraさん、Anarmaaさんは、現在研究技能を磨いていますが、もしかすると指針となるようなロールモデルを見つけることができたかも知れません。
